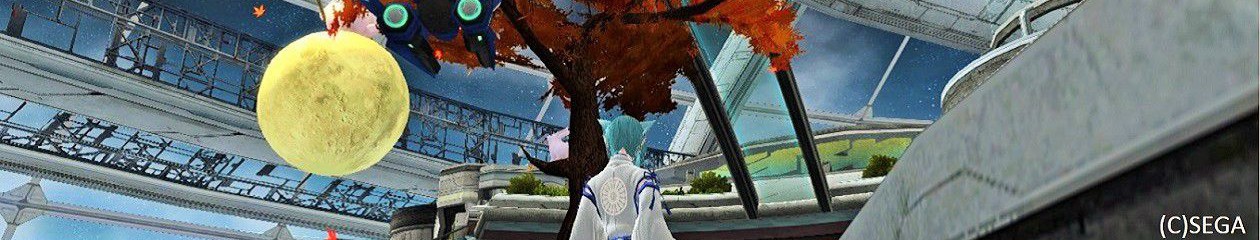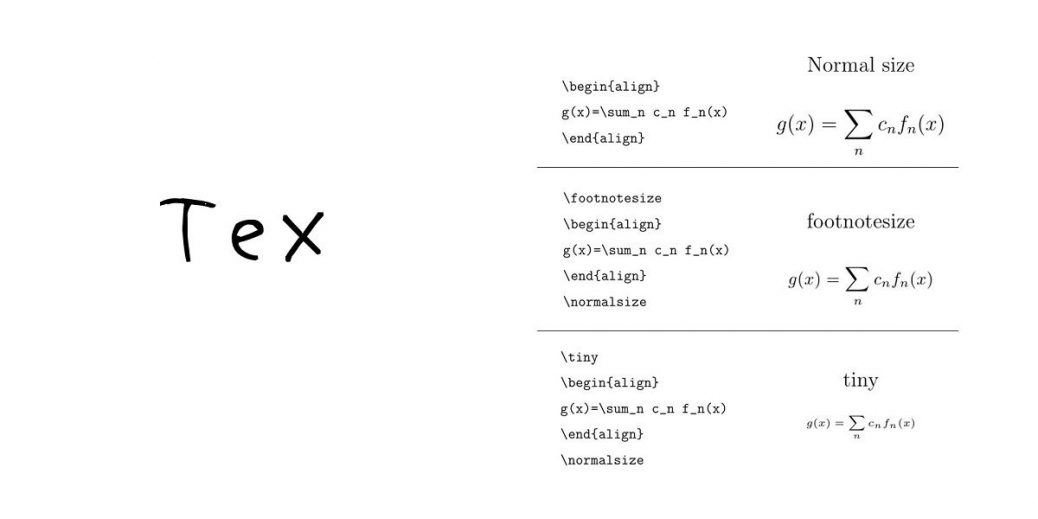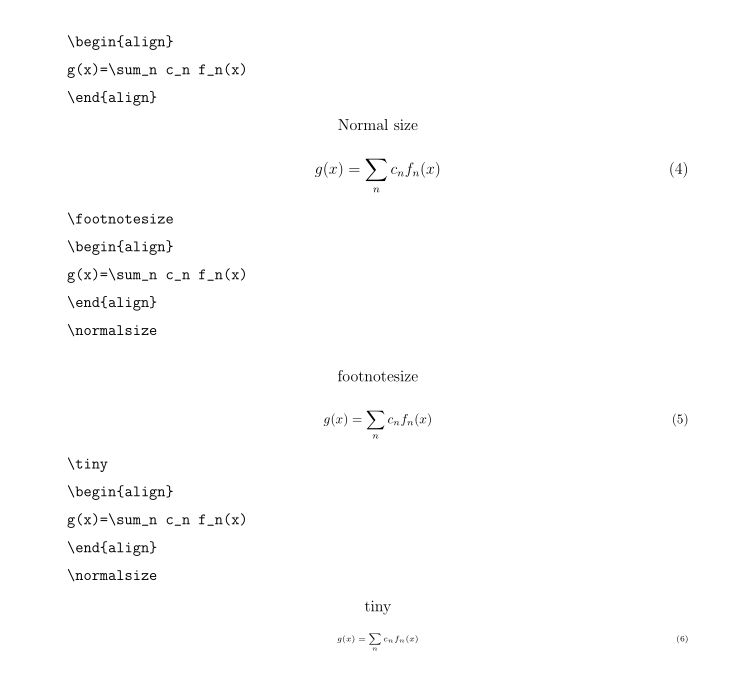数式が長すぎてはみ出してしまう時の対処法
数式全体を小さくするには、数式を挟むように
\footnotesize
\normalsize
と書けばいいです。
\footnotesize
\begin{align}
g(x)=\sum_n c_n f_n(x)
\end{align}
\normalsize
\begin{align}
g(x)=\sum_n c_n f_n(x)
\end{align}
\normalsize
実例
通常だと
\begin{align}
g(x)=\sum_n c_n f_n(x)
\end{align}
g(x)=\sum_n c_n f_n(x)
\end{align}
\footnotesize,\normalsizeで挟むと、
\footnotesize
\begin{align}
g(x)=\sum_n c_n f_n(x)
\end{align}
\normalsize
\begin{align}
g(x)=\sum_n c_n f_n(x)
\end{align}
\normalsize
\tiny,\normalsizeで挟むと、
\tiny
\begin{align}
g(x)=\sum_n c_n f_n(x)
\end{align}
\normalsize
\begin{align}
g(x)=\sum_n c_n f_n(x)
\end{align}
\normalsize
となります。